突然ですが、「自己肯定感」は1994年に臨床心理学者である高垣忠一郎が提唱しました。
20年以上前に生まれた言葉ですが、近年、「自己肯定感」というワードを耳にする機会が増えたと思いませんか?
急速な時代の変化、多様性が広がり「個」が強くなっている今、「自己肯定感」は社会的に重要な概念、力となりました。
変化、競争が激しく、ストレスにまみれた現代社会で、「自分は自分でOK」と感じにくくなっている人が増えているのです。
自己肯定感について知りたい方、自己肯定感を高めたい方は、ぜひ最後までお読みください。
 ともみ
ともみ日本能力開発推進協会認定の「自己肯定感アップカウンセラー」の資格を所有している私が解説します。
自己肯定感ってどんな力?
「自己肯定感」の意味を辞書で調べると、このように書かれています。
自己肯定感(じここうていかん)とは、自分自身の価値や能力を認識し、肯定する心の状態を指す言葉である。
引用元:自己肯定感|weblio辞書
簡単にいうと、「ありのままの自分を認めること」ということです。
「ありのまま」「そのまま」の自分ですので、どんな人にも良い面・悪い面がありますよね。
良い面は「私のこんなところ、イイよね♪」と、ダメだと思う部分を否定したり開き直ったりせず、まるっとそのまま受け止める力といえます。



私が私の一番の味方、という感じですね。
そして、
自己肯定感が、人生の質を左右する
といっても、過言ではありません。
自己肯定感が高い・低いとどうなるの?
なんとなく、「自己肯定感は高い方が良い」というイメージを持たれている方が多いのではないでしょうか。
自己肯定感の高さによってどのような状態になるのか、ざっくりいうと以下のとおりです。
自己肯定感が高い→生きるのが楽になる
自己肯定感が低い→生きるのが苦しくなりがち
順を追って説明しますね。
自己肯定感が高い状態


自己肯定感が高いと生きるのが楽になる理由を挙げます。
- 「そのままの自分」を受け入れているため、自然体でいられる
- 欠点を無理に克服しようとしたり、隠したり、取り繕ったりしない
- 他者からの過度な承認や賞賛を求めない
- 周囲との過度な比較、無用な比較をしない
- 他者との良好なコミュニケーションが取れる
- 前向きで安定したメンタル
- 自分で未来を切り開ける
- 自分を客観視できる
- 自分軸思考
ありのままの自分を認め、受け入れているため、周囲からの評価が気にならなくなります。
また、自分が納得・満足すれば良いので、周囲との比較もしません。
自分がどう思うか・感じるかが大事なので、主導権は自分にあるため、生きるのが楽になり、満足度も高くなります。



決して自分の意見を傲慢にすべて通すという意味ではありません。
周囲との調和を大切にすることもできるし、自分の気持ちを大切にすることもできる。
何を選択するかを自分で決めることができる、ということです。
自己肯定感が低い状態


自己肯定感が低いと、生きることに苦労したり、生きづらさを感じたりすることが多くなる傾向があります。
こちらも理由を挙げてみますね。
- ダメな自分を受け入れられず、自分を好きになれない
- 弱さや欠点を見せないよう、過度な努力・隠す・取り繕うなどの行動に出る
- 他者の承認や賞賛がないと不安になる
- 他者と比較ばかりし、自分の欠点ばかりに目がいく
- 相手の顔色を窺う、相手との適切な距離が分からないなどのコミュニケーション不全を起こす
- うつや不安障害などのリスクが高まる
- 新しいことへの挑戦に恐怖を感じ、前向きになれない
- 不安や恐れが強く、周囲の目を気にする
- 他人軸思考
まず、自分が自分の味方になれていないので、そりゃ不安・恐怖だらけだな、という感じです。
自分自身で受け入れられていないので、周りから評価されないと不安で仕方なくなります。
自分の気持ちよりも他者の意見や感情を優先するため、自分の人生なのに自分に主導権があるとはいえません。
これでは生きることが苦しく、生きづらいと感じるのも当然ですよね。
自己肯定感の高低による人の特徴
自己肯定感の高さにより、物事の捉え方や思考・行動が変わります。
自己肯定感が高い人、低い人の特徴をまとめてみました。
| 自己肯定感が高い人 | 自己肯定感が低い人 |
|---|---|
| ・物事を肯定的に捉える ・失敗しても自分や他人を責めない ・失敗を成長の糧にする ・自分には価値があると思っている ・自分軸が確立されている ・周りに振り回されない ・問題解決能力が高い ・主体性が高く、能動的 ・気持ちが安定している ・自己主張できる ・人生の主導権を握っている ・他者も尊重できる ・柔軟な対応ができる | ・物事を否定的に捉える ・失敗すると自己否定や言い訳、他者を責める ・自分を正当化しないと不安 ・他者に認められないと自分に価値を感じられない ・他人軸で軸がブレブレ ・周りに振り回される ・問題解決が苦手 ・主体性が低く、受動的 ・気持ちが不安定 ・自分の意見を言えない ・人生の主導権が他人 ・気持ちに余裕がない ・完璧主義傾向 |
人生を生きやすいか、生きにくいか、一目瞭然ですね。
ちなみに私は自己肯定感が低い人の特徴にかなり共感できる、自己肯定感の低い人間でした。
そんな自分の思考のクセや生きづらさを解決したいこともあり、自己肯定感アップカウンセラーの資格を取ることを決めたのです。
たとえ自己肯定感が低く、今現在苦しんでいたとしても、安心してください。
自分の思考のクセや行動パターンを知り、自分と向き合うことで自己肯定感は高められますよ!!
自己肯定感の高め方は、後ほど紹介しますね。
参考:自己肯定感とは?|一般社団法人 日本セルフエスティーム普及協会
自己肯定感の育まれ方
自己肯定感が高い人、低い人さまざまいますが、自己肯定感はどのように育まれていくのでしょうか。
それは、生まれてから今までに至る「過去の体験」により、自己肯定感の高さが決まってきます。
生まれたばかりの赤ちゃんの自己肯定感は真っ新で、母親をはじめ保護者との関わりの中で心の土台となる「自己肯定感」を築き上げていきます。
保護者(特に母親)との関係の中で、自分の価値基準やルールをつくり出していくのですが、自己肯定感にも大きな影響を与えます。
たとえば、自分の中の基準やルールが多すぎ、厳しいものであれば、その後の人生で生きづらさを感じやすくなります。
そして、基準やルールが厳しく自分にダメ出しばかりしていると、自己肯定感は下がってしまうのです。



幼少期に人格否定や極端に厳しいしつけをするのは、将来自己肯定感が低い人になるリスクがあると言えます。
「あなたはあなたでOK」と安心感・信頼感を育みながら「自分は愛されている」と実感させてあげると良いでしょう。
自己肯定感の高め方|基本編


自己肯定感は子供も大人も、いくつになっても高めることができると言われています。
しかし、自己肯定感を一度高めても、放っとくと下がってしまうことがあるんです。
では、自己肯定感はどのように高めたら良いのか。
ここでは基本的な自己肯定感の高め方を簡単にご説明します。
- 自分の「今」に目を向け、感じる
- 「過去」を振り返る
- 「自分軸」を育て、確立する
- 人間関係の距離感を学ぶ
- 「夢」を見つける
- 心理的ブロックを外す
- スモールステップで達成を味わう
ものすごくざっくりとですが、上記のステップを踏めば、自己肯定感は上がります。
自己肯定感を高めるには、まずは自分で自分を認めること。
その後に他者との関係を心地よいものにし、自分の夢や目標をすこしずつ形づくる作業をするのです。
もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてくださいね。


私の自己肯定感を高める活動
私は内向型HSPを自覚しており、子供の頃から生きづらさを感じていました。
自分でいうのも難ですが、割と頭の回転が速く、どんなこともそれなりにこなせるタイプでしたので、傍目からは優等生とか何でもできる人とか、順風満帆な人生を歩む人に見られていたかもしれません。
ですが、内面では結構苦しかったんですよね。
そんな私は、社会に出て、結婚し、子供が生まれたことで、自分を見失い、心身共にボロボロになりました。
ですが、どんなに心身共にボロボロになっても、家事も仕事も育児も待ったナシです。



世のママさんなら、「わかる~~~~!!」って方が多いのでは!?(涙)
その暗黒時代に「自分軸」という言葉に出会いました。
そこから、手帳で自分軸を育てる活動を始め、自分と向き合う日々を過ごし今に至ります。
私と同じように、手帳を使って「今」「自分」に向き合いたい人は、以下の記事をぜひ参考にしてください。
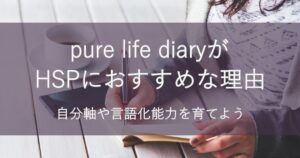
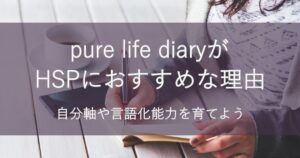
そして、私の夢である「私と同じような内向型さんやHSPさんの心を救いたい」という活動を少しずつ形にすることができています。


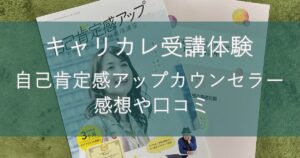
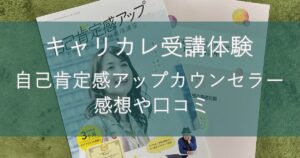
カメの歩みで、活動としては本当にスモールステップですが、自分のやりたいことに向けて活動を継続できています。
これからも内向型さん、HSPさん向けに「心」に関する発信を続けていきたいと思っています。
まとめ


自己肯定感の概要や高い・低い人の特徴、高め方など、自己肯定感に関する基本的な情報を解説しました。
自己肯定感とは「ありのままの自分」をそのまま受け入れて認める力です。
「自分が自分の味方」「自分が自分の一番の理解者」になることで、人生が生きやすくなり、満足度も高くなる素晴らしい能力です。
自己肯定感の高い人と低い人の特徴でも説明したように、自己肯定感は高いに越したことはありません。
今、自己肯定感が低いからといって落ち込むことはありません。
自己肯定感は子供から大人まで、いくつになっても高めることができます。
ただし、放っておくと下がる傾向にあるため、自己肯定感が高い状態でキープできるような思考・行動でありたいですよね。
現在子育て中の親御さんは、ぜひ、お子さんの自己肯定感を育くんであげてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
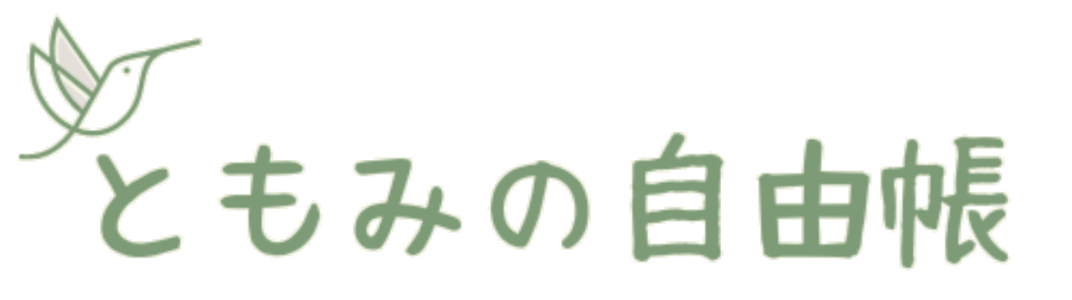
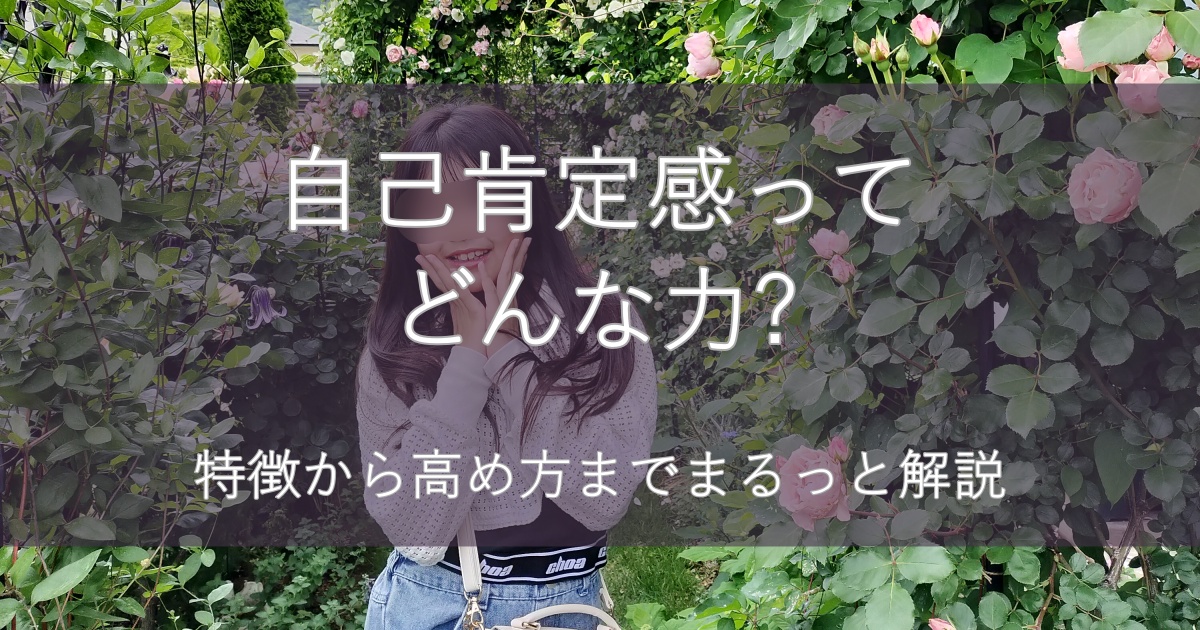
コメント