子供の習い事で不動の人気を誇るピアノ。
長く習っていると、「コンクール出場」がチラつくこともあるのではないでしょうか。
私の娘は4歳からピアノを習い始め、年長さんからピアノコンクールに出場しています。
今までに「グレンツェンピアノコンクール」「全日本ジュニアクラシック音楽コンクール」に出場しました。
その時の経験を踏まえ、小学校中~高学年のお子さんは、どんな曲を選んでいるのか、紹介したいと思います。
 ともみ
ともみエレクトーン歴8年、強豪吹奏楽部出身の私が、娘のピアノコンクールを全力で応援しています。
娘の経験と、ピアノ教室の先生からの情報で記事を書いています。
ピアノコンクールは地区単位のものから全国単位のものまで、大小さまざまあります。
ピアノコンクールにより、課題曲が指定されている場合もありますので、出場したいピアノコンクールの詳細情報は事前に確認しましょう。
選曲が自由である場合、このブログを参考にしていただけると幸いです。
ピアノコンクールで弾く曲の選曲方法
まず、お子さんがピアノコンクーで弾く曲の選曲方法から紹介します。
ポイントとしては、以下の4点です。
- レベルやスキルが合っているか
- 身体的に弾けるか
- 本人の好きな曲か
- 今のレベルより少し背伸びしたレベルの曲がベター
これは私が以前書いた、未就学~小学校低学年くらいのお子さん向けの選曲方法と同じです。
こちらにも詳しく説明していますので、参考にどうぞ。
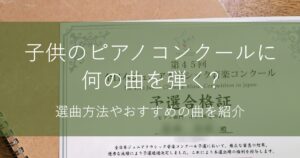
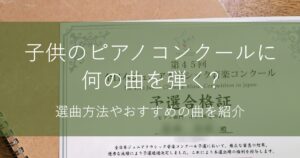
簡単にですが、この記事でも説明していきますね。
レベルやスキルが合っているか
お子さん本人のレベルやスキルはもちろん、出場するコンクールのレベルにも相応しい曲を選曲しましょう。
小学校中学年以降になると、レベルの差がはっきりと出てきます。
お子さんのレベルを考慮しつつ、出場するコンクールで過去に演奏された曲を参考にされると良いでしょう。
身体的に弾けるか
小学生は身体の成長スピードに個人差が大きくある時期です。
弾きたい曲の和音や音の跳躍で指が届くか、まだまだ気に掛けた方が良いでしょう。
学年が上がれば、当然演奏される曲のレベルも上がってきます。
難易度の高い曲に挑戦したいところですが、手の大きさや体の大きさ的に難しい曲は避けた方が良いです。
また、小学校中学年くらいになると、ペダルや足置きの補助台が不要になってくる子もいます。
正しいフォームで弾けるか、本人が弾きやすいかも一緒に確認しましょう。
本人の好きな曲か
曲の難易度や教える側の先生の得意・不得意など考える条件は複数ありますが、本人が好きと思える曲がベストです。
ピアノコンクールに向けての練習は長丁場です。



娘は毎年、半年くらい前から練習をスタートしています。
気の進まない曲より、お子さんの直感で「いいな」「この曲の雰囲気好き」と思える曲の方が、厳しい練習でも頑張れるでしょう。
今のレベルより少し背伸びしたレベルの曲がベター
ピアノコンクールに向けた練習をいつから始めるかにもよりますが、今のレベルより少し背伸びした曲をおすすめします。
娘は半年前から練習を始めますが、毎年「この曲弾けるようになるのか!?」と私が不安に思います(笑)
でも、弾けるようになるんですよね~
指導してくださる先生や、娘の頑張りのい賜物ではあるのですが、子供は伸びます。
そして難しい曲が弾けるようになってくると自信もついてきます。
長丁場でじっくり曲を仕上げていくのであれば、背伸びした曲をおすすめします。
ピアノコンクールで審査しているポイント
ピアノコンクールで、審査員が見ているのは以下の点です。
- 演奏の完成度(ピアノ奏法の基礎、表現、ペダリングなど)
- 譜面どおりに弾けているか(音符、演奏記号などの正確性など)
- 音楽的表現(楽曲の情景、イメージを出せているかなど)
- ステージマナー(ステージ上の所作、お辞儀など)
ピアノの基礎的な能力が習得できているか、はもちろんのこと、譜面とおりに正確に演奏ができているか、その上でどのような解釈でどのように表現しているかを審査されます。
ピアノコンクールにもよりますが、小学校高学年にもなると、かなりシビアに審査され、次の大会への通過も厳しいものになります。
日々の練習は当然とし、自分のレベルに合う曲、好きな曲を選ぶことも合格への重要なポイントになります。
小学校中~高学年におすすめのピアノコンクール曲
では、小学校中学年くらいから高学年にかけて、どんな曲を選んだらよいのか、実際にコンクールで弾かれていた曲を紹介します。
(ブロック装飾)
小学校高学年くらいになると、その子の素質や経験から、レベルにかなりの差が出てきます。
紹介する学年はあくまで目安と考えていただき、お子さんに合った曲を選択してくださいね。
小学校4年生
静かで美しい曲の入りから、中盤では楽し気な雰囲気に変わる
コンクール初心者さんにもおすすめ
スラーとスタッカート、リズム意識できると良い
躍動感のある曲
右手も左手も細かな連打が続く
躍動感、疾走感などを丁寧に表現できるかが鍵
流れるようなワルツが特徴の曲
曲調の変化が美しい
小学校5年生
繊細な小波のような始まりから、中盤で力強くも美しい波を感じさせる曲
丁寧な強弱、自然の波を表現したい
単音が多いが、速い指の動きが求められる
跳躍や腕の交差も多い、軽やかな曲
軽やかで優雅な雰囲気の曲
オクターブの和音や左右の手で弾く音域があまり広くないので、身体が小さい子や手の小さい子におすすめ
小学校6年生
繊細さとダイナミクスさの入り混じる曲
使う音域が広く、多種多様なテクニックを必要とする
上級者向け
明るい雰囲気で美しく流れのある曲
シンプルだからこそ丁寧で、細かなテクニックが光る
楽しく、軽快でノリの良い曲
ちょっとリズムが複雑なところがあるが、リズム感に自信のある子は挑戦してほしい



吹奏楽時代、先輩がアンサンブルで演奏した曲なので、個人的に好きな曲です。
娘が挑戦した曲
私の娘が、小学校4年生の時に実際にコンクールで演奏した曲を紹介します。
参加したコンクールは全日本ジュニアクラシック音楽コンクールです。
全日本ジュニアクラシック音楽コンクール予選
ソナチネ 第9番 Op.36-3 第1楽章
作曲:M.クレメンティ
予選は練習曲のソナチネから選びました。
複雑な和音などはありませんが、指がふにゃふにゃ、リズム感の怪しい娘にとっては、かなり練習になる曲でした。
シンプルな楽曲であるほど、表現力がモロに出てしまうので、練習のし堪えのある曲だと思います。
全日本ジュニアクラシック音楽コンクール本選
タランテラ Op.77-6
作曲:M.モシュコフスキ
最初に譜面を受け取った時、とにかく指の動きが速く、小4の娘が弾けるようになるのか、かなり不安を覚えた曲でした。
ところで、「タランテラ」って、読みの雰囲気が「タランチュラ」に似ていると思いませんか?
実はこの曲、タランチュラに噛まれ「ヤバイ!!どうしよう!!」となっている人をイメージして作られた曲らしいのです。
なんだかおかしな世界観だな、と思いましたが、タランテラの曲も独特な雰囲気があります。
聴いていると病みつきになるというか、中毒性を感じる曲だな、と個人的に思っています(笑)
アップテンポな曲なので、娘は最後の最後までリズム感には苦戦していました。
ノーミスで弾けるくらいにはなりましたが、滑りやすく、ミスタッチに注意です。
まとめ
小学校中~高学年のお子さん向けのコンクール曲の紹介や、選曲方法、コンクールでの審査ポイントなどを紹介しました。
ピアノコンクールは通常のレッスンで弾く曲とは違い、長い月日かけじっくりと練習を重ねます。
じっくりじっくり磨きをかけ、自信をつけてから出場するものですので、お子さんの練習への取り組みはもちろん大事ですが、曲選びも重要なポイントになります。
この記事でまとめた選曲方法や、ピアノコンクールで審査するポイントを押さえ、お子さんに合う最高の1曲を選んでくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
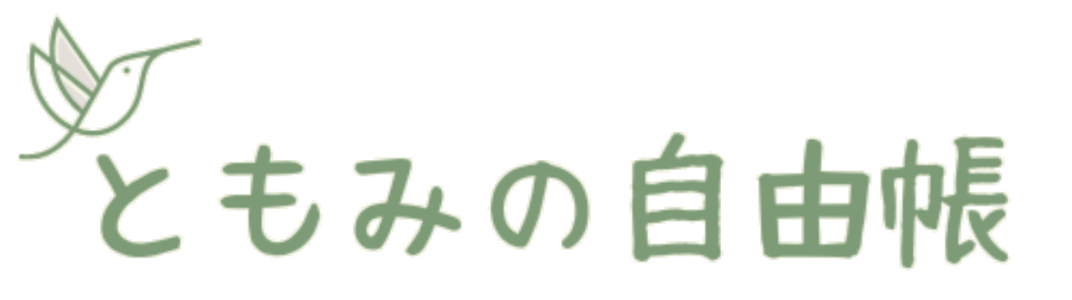
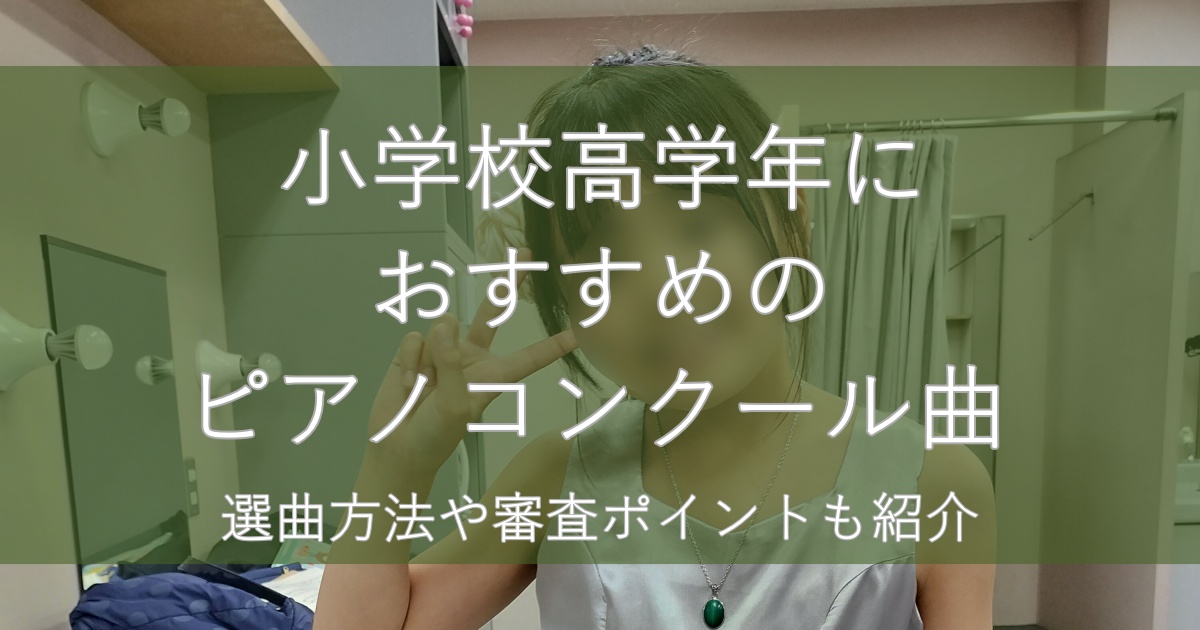
コメント